介護保険には、住みなれた自宅での暮らしを続けることができるように支える制度もあります。
介護保険の制度で住環境に関するものが、「福祉用具」と「住宅改修」です。
住みなれた家での暮らしを続けるには工事が必要になる場合もあります。
この時に使える介護保険サービスが「住宅改修」です。
介護保険を使用すると、費用の一部の負担で「住宅改修」を受けることができます。
ここでは、「住宅改修」の基本的な内容について紹介します。
注意点もありますので、住宅改修を考えている方は、最後まで読んでくださいね。
福祉用具の住宅改修とは
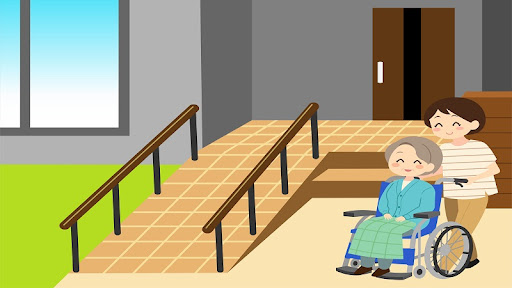
住宅改修とは簡単にいうと、リフォームです。
福祉用具の住宅改修とは、要介護認定を受けた人の家での暮らしをサポートする、介護保険サービスの1つになります。
親が介護が必要な状態になってくると、多くの人が「親が暮らしやすいようにリフォームをしたいけど、お金がかかる…」と考えます。
福祉用具の住宅改修では、リフォームにかかった費用の一部の助成が受けられます。
たとえば、手すりを取り付けたり、段差をなくしてバリアフリーにしたりすることが可能です。
住宅改修というサポートで、要介護認定を受けた人が家での暮らしを続けやすくなります。
福祉用具の住宅改修で補助される対象とは
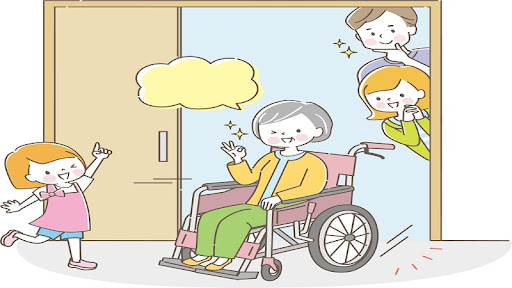
「住宅改修で、色々リフォームしよう」とお考えになる方も多いかもしれませんが、住宅改修はすべての工事が補助される対象にはなりません。
厚生労働省が以下の6つのものに決めているからです。
|
ただし、家の暮らしをサポートする「福祉用具貸与」は住宅改修の対象外ですので、注意してください。
また、「福祉用具貸与」は工事を伴わないので、レンタルになります。
どんな人が使えるの?

住宅改修は、すべての人が使えるものではなく、条件があります。
以下の条件を確認して、住宅改修ができるか検討してください。
|
要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)を受けている
介護保険サービスの住宅改修を受けるには、要介護認定を受けていなければなりません。
要介護認定がなければ、住宅改修の対象の項目だったとしても、全額自己負担になります。
住宅改修を受けたい場合は、必ず要介護認定を受ける必要があるのです。
介護保険被保険者証に載っている家に住んでいる
住宅改修の対象になるのは、介護保険被保険者証に載っている住所の家のみです。
たとえば、調子が悪い間だけなど一時的に子どもの家に住んでいる場合は、対象外です。
介護保険被保険者証に載っている家(住民票がある家)のみ、住宅改修が可能となります。
入院中などではなく、現在家で生活している
住宅改修を受けるには、現時点で家で生活していることが条件になります。
入院中や施設に入所中は、住宅改修を受けることができません。
住宅改修は家で生活をしている人が受けられる、在宅サービスだからです。
そのため、現時点で家で暮らしていることが必要なのです。
しかし自治体によっては、入院中であっても住宅改修が認められることがあります。
退院や退所後の暮らしを整えるために、住環境の整備が必要だと判断される場合です。
退院日などが決まっている場合は、入院中に事前申請や住宅改修を行えます。
退院後、定められた事後手続きを行います。
住宅改修後、退院できない時や施設入所に変更となって自宅に住めなくなった時は、住宅改修費は全額負担になってしまうので、注意が必要です。
可能であれば、住宅改修は事前申請のみ入院中に行い、工事は退院後に行うことをおすすめします。
家の所有者の許可を得ている
介護被保険者証に載っている家が住宅改修を受ける人の家ではない場合は、所有している人の許可が必要です。
たとえば、子どもの家や賃貸の場合です。
所有者の許可なく、住宅改修を受けることはできません。
「住宅改修の承諾書」に所有者の署名と捺印が必要になります。
本人の自立支援を促したり、介護をする人の負担が減る
住宅改修は、介護を受ける人が住んでいる家であっても、制限なく改修はできません。
介護保険は、介護認定を受けた人が住みなれた家での暮らしの継続をサポートするものだからです。
住宅改修を受けて、本人ができることが増えたり、介護をする人の負担が減ることが前提になります。
たとえば、手すりを取り付けて、1人で立ち上がれるようになるなど、利用者の役に立つことが重要なのです。
このため、住宅改修は補助を受けられる対象が決まっています。
詳しくは、前述した「住宅改修の補助される対象は」をご覧ください。
いくらまで補助される?

住宅改修の支給限度額は要介護度に関係なく、1人につき1回限りで、20万円です。
自己負担額は、介護保険負担割合証に1~3割のどれかが載っていますので、確認してください。
たとえば、1割の場合は2万円を自己負担することになります。
住宅改修費はまとめて使うこともできますし、複数回に分けて使うことも可能です。
たとえば、1回の住宅改修の工事で10万円しか使用しなければ、次の工事で残り10万円分を使えます。
ただし、20万円を超えた分は全額自己負担になりますので、注意してください。
自治体によっては住宅改修補助制度があって、20万円を超えた分も補助を受けられる場合があります。
担当のケアマネなどや自治体に相談してみてください。
1回20万円の住宅改修費がリセットされる時は?

住宅改修の支給限度額は1人につき1回20万円ですが、リセットされる時があります。
どのような場合にリセットされるのか、確認しておきましょう。
要介護度が3段階以上上がった時
要介護度が3段階以上上がると、1回だけ住宅改修費を再度20万円分使うことができます。
たとえば、要介護2から要介護5になった時など、住宅改修費がリセットされて、再度20万円分使うことができるのです。
引っ越した時
もともと住んでいた家で住宅改修を受けていたとしても、引っ越した時はリセットされ、再度20万円分を使えます。
ただし、新築に引っ越し先する場合は、住宅改修として認められないので、注意が必要です。
支払い方法は?

住宅改修費の支払いは、「償還払い」と「受領委任払い」の2つの方法があります。
基本的には「償還払い」で行われますが、業者によっては「受領委任払い」を選ぶこともできるのです。
それぞれの特徴について、紹介します。
償還払い
償還払いは、住宅改修にかかった費用の全額を一旦業者に支払います。
1割負担であれば後日に申請をすることで、残り9割が返ってきます。
ですが、まとまった金額を用意する必要があるため、利用者にとって大きな負担になります。
受領委任払い
受領委任払いは、自己負担分の費用を業者に支払うので、利用者の負担が軽減できる方法です。
保険給付分は業者が申請することで、保険者が業者に支払いを行います。
ただし、受領委任払いを行いたい時は、「受領委任払い取扱事業者」として登録された業者で住宅改修を行う必要があります。
指定業者以外で住宅改修を行うと、受領委任払いでの支払いはできませんので、注意しましょう。
まとめ

ここまで、住宅改修の基本的な内容について、説明をしてきました。
|
住宅改修をする時は、介護保険を使って行うことをおすすめします。
介護保険を使わずに住宅改修を行うと、全額自己負担することになってしまいます。
そういった事態にならないように、今回のポイントを頭に入れて、住宅改修を受けましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

